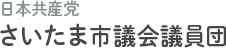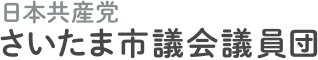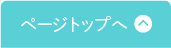市役所本庁舎 移転ありきの計画に疑問
清水市長は、2 月2 日の所信表明で市役所を新都心バスターミナルほか街区へ10年後をめどに移転する方針を明らかにしました。22 日に市庁舎及び行政区の在り方検討特別委員会(党市議団から神田よしゆき・松村としおが出席)が開かれ、都市戦略本部から報告がありました。

昨年、現庁舎の健全性調査で「使用年数が60 年を超えることは適当ではない」との結論が出されました。あと15 年をめどに現地建て替えか移転かの検討が必要な状況です。そのため早く新庁舎に移転したほうがコスト削減できるとの試算や、現時点で新庁舎建設に217 億円、現庁舎解体に12 億円を見込んでいることが報告されました。現庁舎跡地に文化・芸術・教育等の施設整備をするイメージも示されました。
松村市議は質疑で「コロナ対策に全力をあげなければいけないときに市庁舎移転にエネルギーを割くのはいかがなものか」などこの時期の移転発表に疑問の声が寄せられていることを紹介。現地建て替えについて質したところ、市は現地建て替えは検討していないことが明らかになりました。また新庁舎建設と現庁舎跡地開発がセットとなり多額の税金が投入される可能性も指摘しました。引き続き、移転の影響や費用を明らかにさせるとともに慎重な議論を求めていきます。