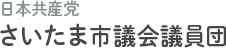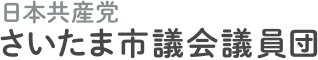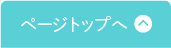2026年2月議会*代表質問 予算組み替え提案で物価高騰対策の拡充求める
2月12日、2月議会の代表質問に松村としお市議がたちました。
松村市議は、昨年度の決算審査で党市議団があきらかにした市民の生活の実情をもとに、「どの世代でも暮らしの厳しさが増している。市民生活と地域経済の現状と見通し、そして行政が果たす役割の認識は」と市長に問いました。市長は「現下の物価高は依然としてここ10年でもっとも高い水準が続いており、市民生活に大きな影響を与えている」と述べ、デジタル地域通貨に4.6億円を使うなど新年度予算案の事業をいくつか紹介しました。
松村市議は「市民の暮らしを支えるために税金を使うのが最優先だ」として、党市議団による約204億円の予算組み替えを提案。決算のたびに増え続ける財政調整基金など基金の一部取り崩しや、大規模事業の見直しなどで財源をつくり、地域経済支援、福祉・医療・教育・公共交通の充実で暮らしの安心を支えるとともに、社会保険料の引き下げなど負担軽減を実現するよう求めました。しかし副市長は「各種基金等の大幅な取崩しによる市民負担軽減や市内事業者支援などをおこなう予算の組み替えは、持続可能で規律ある財政運営の観点と適正な受益者負担の観点等から多くの課題がある」として、提案を拒否しました。
また予算組み替え提案のなかで個別に答弁を求めた水道料金基本料金無料の2カ月延長(8・9月)と住宅リフォーム助成制度の創設についてはいずれも実施を否定しました。
国会質問と連携
食肉卸売市場・と畜場は存続せよ
続いて松村市議は、昨年11月に突然廃止が発表されたさいたま市食肉中央卸売市場・と畜場の存続を求める質問をしました。
関係者から「事前の話がなにもなかった」「報道で知った」との声が党市議団に寄せられていることを紹介し、関係者への説明や協議を検討過程でおこなわなかった理由など、この間の経過について質しました。副市長は「ぎりぎりまで移転再整備事業の可能性を模索したが、安定した運営の実現は不可能と判明した」と答弁。松村市議は「さいたま市だけで結論を出していい説明になっていない」と再度答弁を求めましたが、副市長は説明することができませんでした。市の都合のみを述べるばかりの答弁に松村市議は「到底納得しうるものではない」と厳しく批判しました。
市の廃止方針について、昨年12月に岩渕友参議院議員が農林水産委員会で国の対応を質問しています。農林水産大臣は「公正な取引の場として高い公共性を果たす必要がある」「廃止ありきでなく、市場内外の関係者との合意形成と現場に寄り添った対応をおこなうよう指導した」と答弁しました。松村市議は上記の国会答弁を紹介してさいたま市の対応を質しました。副市長は「卸売市場の公共性について同様の認識をしている。国・県との連携体制のなかで、廃止に伴う雇用や流通、畜産への影響等に対する方策等について検討し、また、関係事業者のご意見をうかがいながら対応策を検討したい」と廃止ありきの姿勢での答弁でした。松村市議は、と畜場の牛・豚の受け入れ実態を紹介するとともに、市の市場・と畜場を「本県における食肉の流通拠点としての役割を果たす拠点施設」と県の計画で位置付けていることを示し、「事業関係者はもちろん、国および埼玉県等関係自治体といっしょに存続に向け協議をおこなうべき」と提案しました。副市長は「市場の廃止にともなう課題と対応についてていねいに検討したい」と同様の答弁をするにとどまりました。
レジャープール削減方針の
撤回求める
松村市議はさらに原山市民プールをはじめ市内レジャープールを5つから2つに減らす「レジャープールのあり方方針」の見直しを求めました。松村市議は原山市民プール存続を求める署名が2万筆を超えて市に届けられ、プールを使う子どもたちから「夏の楽しみ」「なくさないで」とメッセージが寄せられていることを紹介。「建設費高騰と物価上昇が続くなか、今あるレジャープールの存続を前提に、子どもの意見をしっかり聴いた方針につくり直すべき」と求めました。副市長は「方針見直しは予定していないが、財政負担を最小限に、充実した市民サービスの提供が重要。原山市民プールは可能な限り有効活用したい」と答弁しました。