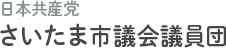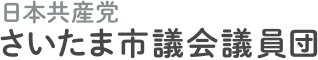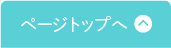2020年4月15日
新型コロナウイルス感染症に対する要望書
日本共産党さいたま市議団
団長 神田義行
市執行部の皆様におかれましては、非常事態宣言のもと新型コロナウイルス感染症への対応に日々ご尽力いただいておりますことに敬意を表します。
感染の広がりも国の対応も流動的ななかではありますが、党市議団に届けられた新型コロナウイルスに関する市民要望をとりまとめたものをお伝えします。どれも切実な要望であり、誠実な対応を求めるものです。
1.市民の命と健康を守る体制構築について
①発熱者の来院を拒む病院も出てきていることから、市として医師会と連携して発熱外来を設置すること。
②感染者の増加が続いているもとで保健所・保健センターの業務量が今後も増加し続ける懸念があることから配置見直しにとどめず全体の人員を抜本的に増やすこと。
③感染拡大を抑えるためにも検査体制と医療体制の拡充にいっそう注力すること。軽症者の隔離施設も県と連携してさらに確保すること。その際、国も含めた公的施設の活用も検討すること。
④医療・福祉等、市民の命と生活を支える施設でのマスク・消毒液等の物資が引き続きひっ迫しており、今後も市として現物での支給にとりくむこと。
2.市民のくらしと営業を支える対応について
①税・保険料・公共料金等の納付や市奨学金返還において困難が生じている市民に対し、4月1日付総務省自治税務局企画課通知の内容を徴収に関係する全ての職員に徹底し、猶予等柔軟な対応をすること。
②国民健康保険税の減免規定において新型コロナの影響による収入減を災害と同等とみなして対象とすること。必要であれば条例改正を行うこと。
③市民生活・地域経済が急速に悪化しており、他自治体では様々な独自支援や給付が打ち出されている。本市においても早急に具体化すること。あわせて水道料金の値下げ、給食費の値上げ中止等市民負担の引き下げを緊急に行うこと。
④市が関与する融資事業において税の完納を条件とすることなく金融機関にたいし速やかな融資の実行を要請すること。
⑤市の奨学金の貸与人数の拡大および要件緩和を行うこと。
3.子どもに関する対応について
①放課後児童クラブや学校で預かる児童に給食施設を活用した昼食の提供を行うこと。
②民間放課後児童クラブにおいて、子どもの感染リスクを下げるため登園自粛を要請しているが、休んだ児童の保育料を返還する際、当面は市が運営費等への補填をすること。
以上