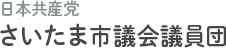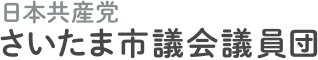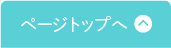子どもの実態と親のねがいにこたえた療育・教育を ~ひまわり学園保護者と懇談~
党市議団は6月29日、さいたま市障害児総合療育施設ひまわり学園に子どもが通う保護者との懇談を行い、とばめぐみ、金子あきよ両市議が参加しました。
ひまわり学園については「親子分離で療育が受けられる日数・時間を伸ばしてほしい」という保護者の要望を受けて、議会で看護師の増員を求め、実現してきた経過があります。保護者からは「まだまだ日数も時間も短い。せめて療育時間を幼稚園と同じくらいにしてほしい」また「人工呼吸器を装着している子どもは保護者が自家用車で送迎しているが、危険で負担も大きいので、バスでの送迎をしてほしい」など切実な要求が語られました。とば市議は6月議会の保健福祉委員会で、学園が保護者と定期的な懇談を行うことを確認しましたが、実態把握とさらなる改善が求められます。
さらに、特別支援学校についての要望も出されました。市立の肢体不自由特別支援学校(ひまわり、さくら草)は定員が少なく、入学希望者が定員を超えると抽選による選抜が行われます。入れなかった児童は市外の県立特別支援学校に入学せざるを得ないため、通学時間が110分にもなる遠くの支援学校に通わなければならないケースもあるということです。金子市議は「適切な環境で教育が保障できるよう、特別支援学校の定員増などにもとりくみたい」と話しました。