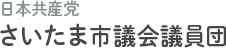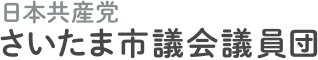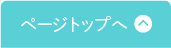2023年9月議会*保健福祉委員会議案外質問 障がい児を性暴力から守るために
9月議会 常任委員会議案外質問(9月19日)
久保みき市議は、3つの課題をとりあげました。
本年7月、岩槻区の放課後等デイサービスの職員が施設利用の女児に対する性的暴行で逮捕されました。5月には、県内在住の重度脳性麻痺のある女子が性被害を受けました。久保市議は、親御さんが日本版DBS(※)の対象に障がい児・者施設もいれるよう求めていると紹介し、「市から国に働きかけるべき」と主張しました。
次に、7月末に市内の私立認可小規模保育施設(19名定員・0~2歳児対象)が閉園した件について、質問によって小規模保育施設は4月の時点で満員になることは難しく、満員でないと赤字になる実態が明らかになりました。久保市議は、0歳児については在籍数ではなく定員数で委託費を出すしくみに変えるよう提案。あわせて「私立であれば経営悪化による撤退があってもおかしくない。公立保育所削減方針は見直すべき」と主張しました。
続いて、ペットショップチェーン最大手会社で顧客トラブルが続発している問題をとりあげました。繁殖場はゴキブリだらけ、ネズミも走り回る環境です。大量生産、利益しか考えない。この会社には動物愛護の意識は皆無です。このような犯罪を野放しにさせないための方策を求めたところ、市は、抜き打ち検査についても検討していくと答弁しました。
※日本版DBS…子どもに関わる仕事をする人を対象にした、過去の子どもへのわいせつ行為・性犯罪歴がないことの証明を求める制度。こども家庭庁が導入への検討を進めている。