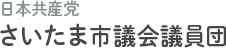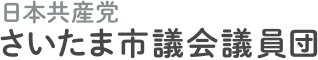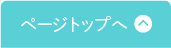2023年12月議会*一般質問 文化財も自然も守るために
12月6日、12月議会の一般質問に久保みき市議がたちました。内容は1、文化財保護と自然保護について 2、循環型社会に向けて 3、防災について 4、別所沼公園の釣り糸等被害について 5、学校のウサギ等の飼育についてです。
さいたま市の文化財の数は政令市で3番目であるのに対し、文化財保護予算はとても少なく、管理が行き届いていないと指摘し、桜区塚本荒川堤外にある「薬師堂のマキ」は入り口案内の看板はなくなり、説明看板は浦和市のままだと写真を示しました。「もっと予算を増やし、政令市3位にふさわしく保護、管理するべき」と主張したのに対し、市は「看板については順次直していく」と答弁。質問後すぐに説明看板は浦和市からさいたま市に変わりました。
「薬師堂のマキ」周辺にはハンノキの自然林があります。さいたま市の蝶であるミドリシジミの食性に必要なハンノキ林は、全国的にも貴重です。準絶滅危惧種の植物も多く貴重な自然が残っています。堤外は農地としては認められていますが、居住はできません。そのために農作物の盗難や不法投棄の温床となっています。久保市議は「このままでは貴重な自然が失われてしまう。国は、生物多様性からさらに進んだ『ネイチャーポジティブ』の考えを示している。ネイチャーポジティブとは、自然は資本である。人類存続の基盤としての健全な生態系を確保し、生態系による恵みを維持し回復させ、自然資本を守り活かすとりくみをしていくということ、その立場に立って塚本、荒川堤外里山を守るべき」と求めました。
また、荒川第2調節池の建設現場が隣接していますが、調節池内水路(囲ぎょう堤脇)は保守点検が楽なように3面張り水路という底も両サイドもすべてセメントで固めたかたちになる予定です。これでは生態系や景観に配慮することが難しく、水の流れが早くなり、水生植物や魚などの生息・生育に適した環境を作ることができない、二面張り水路や土水路にすべきと国に意見すべきと提案しました。
さらにサクラソウ自生地の保全についても質問しました。作業員の勤務日数が減らされた問題、伐採が必要な樹木が残されている問題などを指摘しました。市は、「伐採については検討する」と答弁しました。
生ゴミのリサイクルを求めて
2では、「生ごみ、まだ燃やしますか?」と切り出し、「生ごみは水分量が多く、燃やすためには多くのエネルギーが必要。現在のペースで生ごみを焼却し続けるのは、限界が来ていると指摘している専門家もいる」とし、生ごみのリサイクルを求め、ゼロウエイスト宣言に向けてとりくむよう求めました。市は、生ごみリサイクルにとりくんでいくと前向きな答弁をしました。
3については、2019年の台風19号で甚大な被害が出た、桜区油面川流域の対策として整備された油面川排水機場の計画されているポンプの増設について質問しました。今年6月の大雨では、排水機場の稼働により浸水は免れたものの、油面川の水面は路面ギリギリのところまで来ていました。ポンプを早く増やすべきと求めました。さらに鴻沼川流域についての対策について質問したところ、市は、県が決めていると答弁しました。久保市議は「市独自では、なにもしないということか」と強く迫り、市は「できることはしていく」と答弁しました。
釣り糸 ポイ捨てしないで
4は、別所沼公園の釣り人がポイ捨てした釣り糸、針によって多くの野鳥が苦しんでいる実態を、片足を失ったバンの写真や釣り糸が足に絡まりついた鳥の写真で示しました。公園のごみ拾いの徹底と「ポイ捨て禁止」の啓発の看板を大きな効果的なものに変えるよう求め、市は、清掃、看板、改善すると約束しました。
5は「ウサギを飼育する際の適正温度は、18〜24℃。気温の変化に弱いウサギは、室内飼いが望ましい」と指摘しました。ウサギは草食動物で、丸1日(半日とも)絶食状態になると内臓に障害を起こし、最悪の場合死につながることがあるといわれていますが、学校は土日が休日で多くの学校のウサギたちは丸2日絶食状態で、「確実に動物虐待と言える行為」と強く指摘しました。学校で動物を飼育する目的は、生命の大切さや思いやりの心を育てることであるはずです。それがもはや、大切な命をそまつにあつかっていいという教育になっており、学校での小動物の飼育を見直すべきと求めました。市は答弁で、飼育方法を改善することを約束しました。