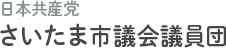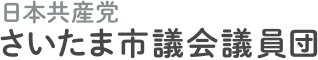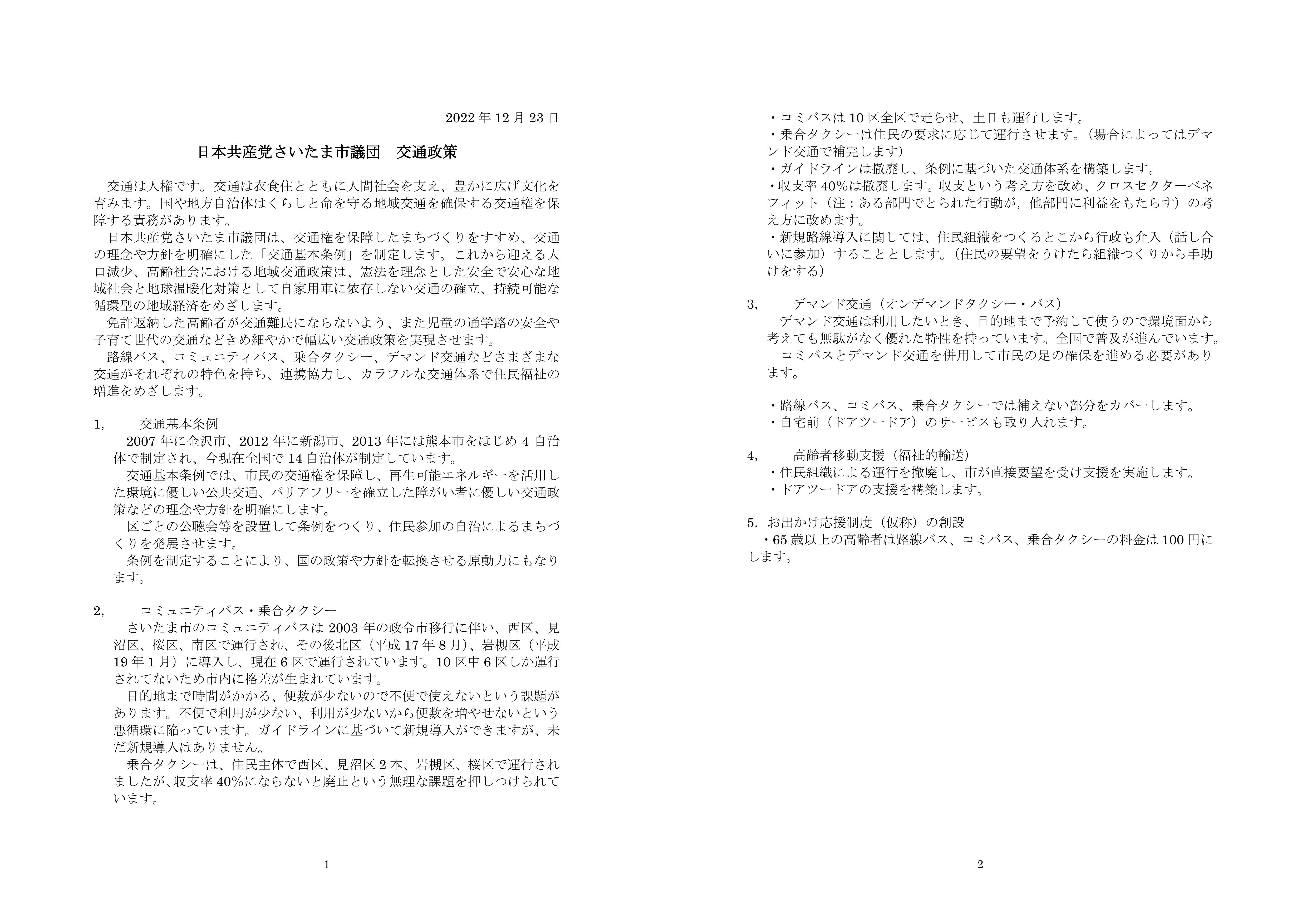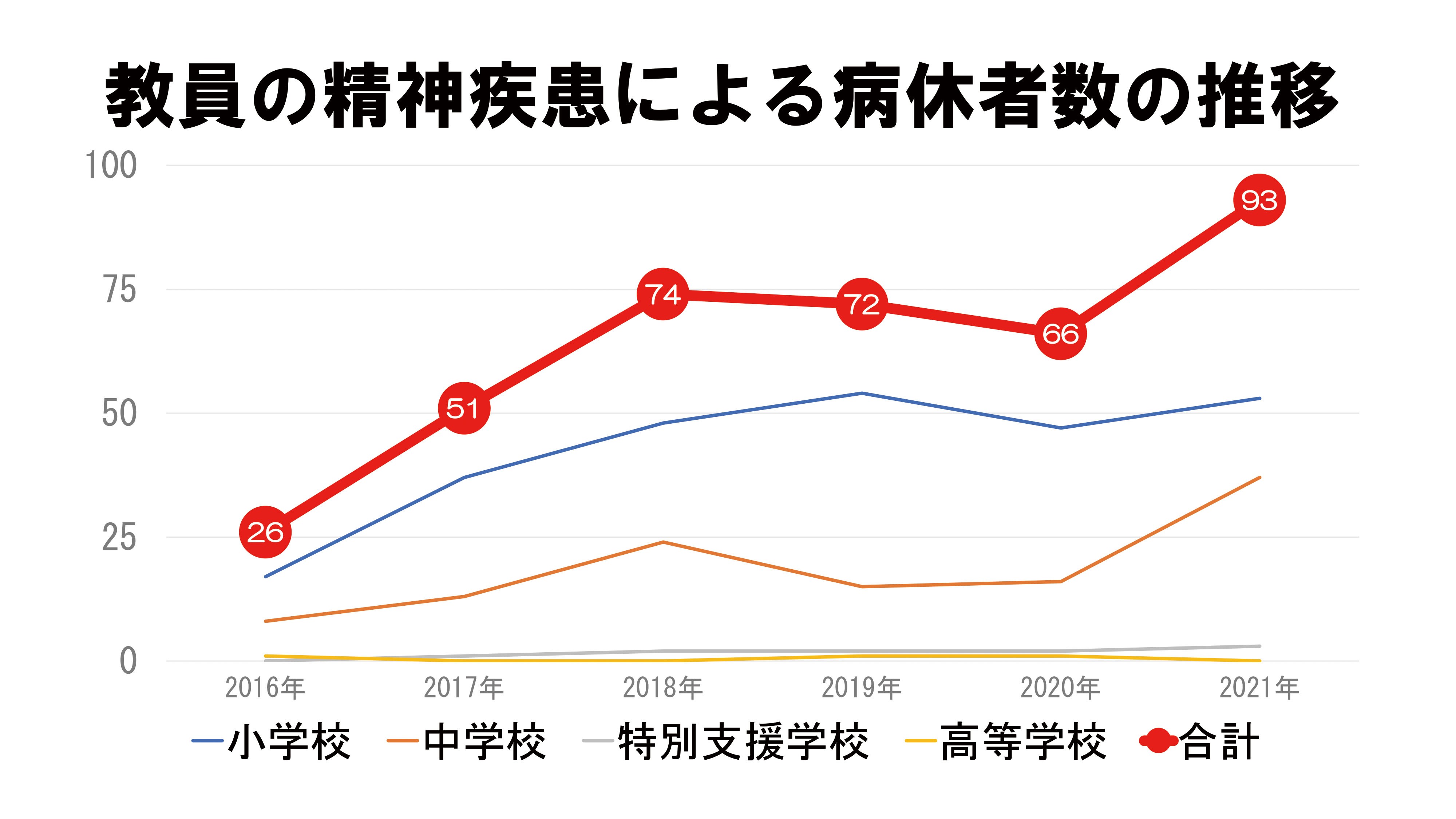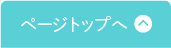与野中央公園に5000人収容のアリーナ建設?!
さいたま市が(仮称)次世代型スポーツ施設基本計画を公表しました。この計画は与野中央公園(新中里4-7-2)に5000人を収容できるメインアリーナと中央区役所周辺の公共施設再編計画によって取り壊される与野体育館の代替施設としてサブアリーナを合わせて建設する計画となっています。住民への十分な説明もないまま、この計画を進めていいのでしょうか。主要な論点を紹介します。
くさはら広場の面積が8分の1に減少
与野中央公園の全体敷地面積は8万1000㎡ですが「次世代型スポーツ施設建設」により、残されるくさはら広場の面積1万4000㎡となり、残りは原則、コンクリート舗装となります。敷地面積に対してメインアリーナが巨大すぎるのではないでしょうか。
当初のイメージからかけ離れてしまう
もともと、与野中央公園の在り方は旧与野市時代から市議会で議論されており、中央公園基本計画(昭和63年)や与野中央公園基本計画(平成5年)では「みどりと水辺が豊かな居心地の良い空間を創造する公園」とのイメージが示されています。 アリーナ建設はこの当初のイメージからかけ離れてしまうのではないでしょうか。
アリーナは誰のための施設?
メインアリーナの想定利用シーンは「プロバスケットの試合、アイスショー、プロレス、ショーイベント、企業のコンベンション・展示会、大規模市民大会(パブリックコメント実施後に追加)」などが示されており、市民利用は限定的です。市民利用がメインでないハコモノに多額の税金を投入する正当性が問われます。
採算は取れるのか?
市が提出した資料によると、アリーナの建設費は約72億円、ランニングコストが約6億円で、収入に対して約1.3億円の年間赤字がでるとされています。市は、パブリックコメントへの回答で「黒字化できる」としていますが、根拠は示されていません。
誰がこの計画を主導したのか?
市は3月におこなわれた説明会で「誰がいつ決めた計画なのか」という質問に対して「令和3年度にスタートした総合振興計画で決めた」と回答しました。この計画はさいたま市の最上位計画で市長が取りまとめ、議会に了承を求める計画です(党市議団以外の全会派が賛成)。市民の要求に基づいた計画ではなく、事実上、「市長のトップダウンで決めた」と同義語です。
公園利用や周辺環境への影響は?
実際にアリーナができた際の公園利用や周辺の住環境への影響についても多数の懸念が寄せられています。例えばアリーナの高さは20mが想定されていますが、その北側にある「くさはら広場・遊具場」は今でも休日になればたくさんの子どもや親子連れが利用しています。その場所の日当たりが悪くなることへの懸念です。
また5000人を収容するアリーナを建設するのに用意されている駐車場は200台のみでアリーナでイベントをおこなう土日や祝日などは、通常の公園利用者とイベント参加者で駐車場を取り合うことになり、市民利用に大きな影響が出ることも想定されます。
周辺の住環境への影響も当然、指摘されています。例えば、与野中央公園のゾーニングイメージによると駐車場の出入り口は1カ所しか用意されておらず、渋滞を誘発しやすい構造になっています。公園が面する中央通りは大宮区桜木町から中央区大戸までを横断する主要道路で、中央区民の生活環境への多大な影響が予想されます。加えて、イベントをおこなう際の「騒音」への対策など、市民への説明が必要な論点を挙げれば、キリがありません。
中央区選出のたけこし連市議は「中央区には、埼玉県が誇るさいたまスーパーアリーナがあり、与野中央公園に建設されようとしているアリーナと利用想定が重なっている。地元の市民は与野市時代から緑と水が豊かな公園になることを期待していたにもかかわらず、この計画変更は唐突すぎる。市の問題点として、市民のためではないハコモノ建設に多額の税金を投入することを指摘したが、まさにその典型例だ。市議団としてアリーナはつくるべきではないと主張し、市民が誇れる公園にしていきたい」と話しました。